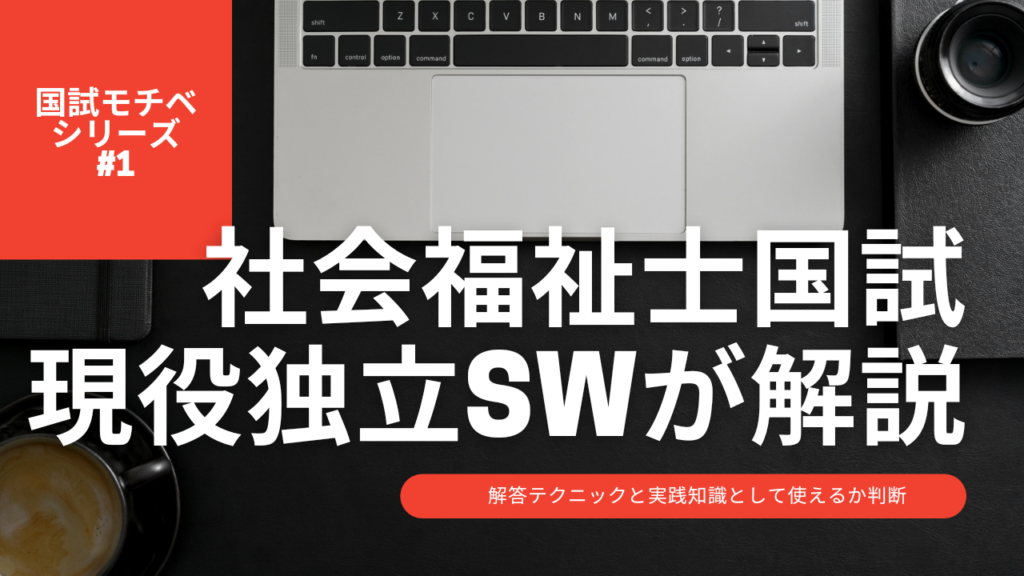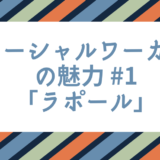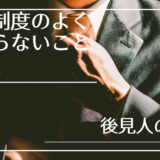目次
実践応用術
まえおき

現役の独立社会福祉士の視点で、実践への応用術を解説します。開設できるということは、実践に使える知識が国家試験の中には詰まっているということです。それにより、将来の仕事のためにも役立つならと、モチベーション維持になります。
実践に使えるか?

この問題の知識は、がんに関する知識です。
その知識を必要とするケースは、がんを罹患したクライエントとの関わりがあるときです。
具体的には、治療法、ステージ、緩和、終末期などの場面で使える知識です。
まず、がんが「治るがん」となってきているものがあることは知っておくべきです。クライエントと話をするときの雰囲気を作る場合、安心感をそこに加えることができます。
また、治療法で「化学療法、手術療法、放射線治療」があり、がんの症状によって、どの手段をとりうるかということとなります。実際のとりうる治療法の判断は、医師が行いますが、いくつか選択できる場合に社会福祉士の出番です。
僕のケースでは、クライエントは喉頭がんでした。芸能人でいうところのつんく♂さんです。
喉頭がんの進行具合によって、化学療法、手術療法、放射線治療のすべてが選択肢のベースとなります。
クライエントは、「声をなくしたくない」という確固たる意思をもっていました。そうすると「手術療法」は選択肢から外れる方向となります。このとき大事なことは、手術療法をしないということは、この先どういうことが予想されるかということを医師と一緒に確認する必要があります。その上で、クライエントが判断するのであれば支持しましょう。
喉頭がんは、進行すると気道が動がふさがり呼吸困難となります。その段階で喉頭全摘をすることになります。
この流れを、知っておくことが実践に使えることであり、国家試験の問題にはそれだけ深堀できます。
がんの治療法についても常日頃アンテナをはっておくと、最近新たに「光免疫療法」という治療が出てきたということも知識として仕入れることができます。これがどんな治療で、どんなことに配慮すべきか、誰が治療を受けることができるのかなど、クライエントと一緒に勉強することも大切です。
最後に
いかがでしたでしょうか?
自分が国家試験を受けるときに「あったらいいな」を形にしてみました。とりあえず、継続してみます。
不評であればすぐにやめます(笑)